災害大国・日本では、地震・台風・豪雨などによる自然災害が毎年のように発生しています。そうした状況下で見落とされがちなのが、「ペットの安全」です。特に犬や猫を家族同然に飼育する方にとっては、避難所での対応や災害時の備えが大きな不安材料となっています。
ペットの防災意識は年々高まりを見せており、「避難所にペットを連れて行けないことへの不安」「防災グッズの不足」「日頃の備えに何が必要かわからない」など、飼い主の悩みは多岐にわたっています。

ペット防災の現状と課題
一般社団法人ペットフード協会の2024年データによれば、現在日本では犬が約679.6万頭、猫が約915.5万頭飼育されており、ペットと暮らす家庭は社会の中で大きな割合を占めています。この膨大な数のペットと飼い主が、災害発生時に一斉に避難行動を迫られるのです。
しかし、現実の避難所では、「ペット不可」や「ケージのみ可」など対応はまちまちで、飼い主が車中泊を余儀なくされる例も少なくありません。実際、令和6年の能登半島地震では、多くのペット連れ避難者が車内での生活を強いられ、寒さやエコノミークラス症候群といった二次被害の危険にさらされていました。ペットは家族同然の存在であるにもかかわらず、災害時には社会から切り離されやすいという現実が、改めて浮き彫りになったのです。
「同行避難」から「同室避難」へ──ペット避難の新たなスタンダード
このような現状を受けて、国や自治体は「同行避難」(ペットと一緒に避難すること)を推奨していますが、それだけでは不十分です。避難先でペットと別の空間にいなければならない「同伴不可避難所」では、飼い主のストレスはもとより、ペットの健康や精神面の悪化も懸念されます。
そのため、今後のスタンダードとなるべきなのが「同室避難」です。これは、飼い主とペットが同じ空間で避難生活を送れる体制のこと。実際に2023年、歌手の伍代夏子さんが発起人となり「りく・なつ同室避難推進プロジェクト」が始動。災害時にペットが孤立しないための制度整備や支援活動を全国に広めています。
ただし、同室避難には課題もあります。動物アレルギーを持つ人、ペットが苦手な避難者、高齢者、子どもなど様々な人が共に暮らす避難所では、衛生・安全・騒音・脱走対策といった配慮が必要不可欠です。
そこで私たちペット快適工房は、「モノづくりの力」でこの社会的課題の解決に貢献できると信じています。

OEM製造で支えるペット防災のかたち
私たちはEVAやネオプレンといった発泡素材、縫製加工技術を活かし、ペット防災分野に特化したOEM製品を提案・開発しています。
▷ 防水・断熱マット
- ネオプレン素材で冷気遮断
- コンパクトに丸めて持ち運び可能
- 防臭・防水加工で衛生的
▷ ペット防災バッグセット
- フード、水、トイレシート、薬などを1つに収納
- 飼い主の負担を軽減する設計
- 高齢者や女性でも扱いやすい設計
▷ 自治体向け「避難所用ペットスペースキット」
- ケージ、マット、簡易パーテーションをセット化
- 地方自治体や医療機関への備蓄提案
- 同室避難を支えるインフラ製品群
飼い主が備えるべき防災対策──災害時に“愛犬・愛猫を守る”ための実践ポイント
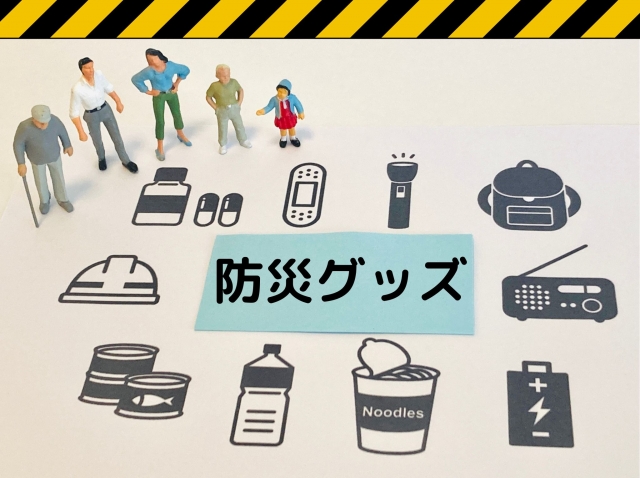
災害は、ある日突然やってきます。大切なペットを守るためには、日頃からの備えが何より重要です。以下では、環境省・厚生労働省の指針も参考にしながら、飼い主が行うべき具体的な5つの防災対策を詳しく紹介します。
① 同行避難先の事前確認と避難行動計画
環境省は「災害時にはペットとともに避難すること(=同行避難)が原則」と明示しています(環境省:ペットの災害対策ガイドライン)。
しかし、「同行避難=同室避難」ではないことに注意が必要です。避難所によっては、ペットは屋外の仮設スペースに置かれる場合もあり、車中泊を選ぶ人も多くなります。
そのため、以下のような備えが必要です。
- 自治体の避難所リストをチェック(ペット可かどうか)
- 複数の避難先候補(親族宅、知人宅、ペットホテル)を想定
- 防災訓練の実施(実際にケージに入れて避難ルートを歩く)
「うちはマンションだから関係ない」と思っていても、断水・停電・エレベーター停止などで生活不能になる可能性があります。必ず事前確認をしておきましょう。
② ペット用防災グッズの備蓄と整備
災害直後は物流が止まり、必要な物資が手に入りません。最低でも5〜7日分のペット用防災用品を備蓄しておくことが推奨されています。
【準備すべき防災セット例】
- フード・飲料水(最低5日分、普段食べているもの)
- 常備薬(持病のある場合は予備を処方してもらう)
- 折りたたみケージやキャリー(避難先での居場所確保)
- 迷子札付きの首輪/ハーネス/リード
- 排泄用品(ペットシーツ、ビニール袋、消臭スプレー)
- タオル、毛布、保温マット
- 飼い主とペットの顔写真(迷子になった際の再会用)
- ワクチン接種記録・健康手帳・マイクロチップ番号の控え
特に療法食・薬が必要な子は、2週間分を推奨する獣医師もいます。災害直後に「いつもの餌がない!」と焦らないよう、ローリングストックを習慣にしましょう。
③ 健康管理とストレス対策
避難生活では、ペットも大きなストレスを抱えます。健康でいるためには、日頃からのしつけ・習慣化・ケアが重要です。
【ポイント】
- ケージ・キャリーに慣れさせる:普段から“安心できる居場所”として認識させておく
- 「まて」「おいで」「静かに」などの基本指示:避難所での安全確保に直結
- 定期的な健康診断、ワクチン・ノミダニ予防の実施
- 高齢・持病・障がいのあるペットには個別のケア計画を
環境省も「ペットのしつけ・健康管理は飼い主の義務であり、災害時にはより一層求められる」と指摘しています(環境省:人とペットの災害対策ガイドライン)。
④ 個体識別と迷子対策の徹底
地震や混乱の中でペットが逃げ出してしまうことは珍しくありません。ペットを確実に識別できる手段を準備しておくことは、再会のために非常に重要です。
- 首輪に名前・電話番号を書いた迷子札
- マイクロチップ(できる限り全ペットに装着を)
- ペットと一緒に写った写真をスマホ・紙で携帯
- 登録情報(マイクロチップ情報)は最新か確認
厚生労働省は、マイクロチップの装着と登録が義務化された(2022年6月以降販売の犬猫)ことを受け、一般飼い主も自主的な登録を推奨しています(厚労省:マイクロチップ登録について)。
⑤ 周囲への配慮と地域との連携
避難所は「共有空間」です。他の避難者が動物嫌いだったり、アレルギーを持っていることもあります。災害時にトラブルを起こさないよう、日頃から「社会の一員」としてのしつけと気配りを心がけましょう。
- 鳴き声・匂い・排泄物の管理に責任を持つ
- ゲージ内で過ごせる練習をしておく
- 地域の飼い主仲間と「助け合いネットワーク」を作る
また、動物病院・トレーナー・地域ボランティアと連携し、ペット避難支援の仕組みづくりに参加することも、防災意識を高める一助となります。
ペットと飼い主を守る製品開発で社会に貢献
災害時に「ペットと一緒にいること」が飼い主の心の支えとなり、ペットにとっても安心できる環境です。その安心を生み出すためには、避難所の環境整備と飼い主自身の備え、そしてその両方を支える製品・サービスが必要です。
私たちペット快適工房では、ペットと飼い主が共に安心して避難できる社会を目指し、機能性・衛生性・快適性を兼ね備えた製品を開発し続けています。
最後に
「災害はいつ起きてもおかしくない」と多くの人が思いながらも、備えが不十分なまま日常を過ごしているのが現実です。ペットを守る備えは、「飼い主の安心」だけでなく、「避難所全体の秩序や安全」にもつながります。
OEM製品でペット防災を支えたい、という企業様や、製品開発に関心のある動物病院・ペット関連事業者・猫カフェ運営者・トレーナーの皆さま──ぜひ一緒に、災害に強いペット共生社会を築きましょう。

